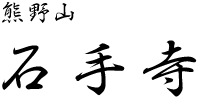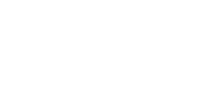道後温泉のほど近く、子宝と健康の祈願が叶う1300年の歴史ある神秘の寺
石手寺(いしてじ)は、奈良時代の728(神亀5)年に聖武天皇の勅願に応じ、伊予の太守・越智玉純(河野玉澄とも知られる)が夢でこの地は霊場だと感得し、熊野十二社権現(くまのじゅうにしゃごんげん)を祀る道場として創設されました。
真言宗の歴史ある寺として、国宝や重要文化財を多数守り続け、四国八十八ヶ所霊場の第51番札所としても名高いです。
本尊(寺の中心となる仏)の薬師如来は、心身の癒しをもたらすと信じられています。また、子の守護神である鬼子母神(きしぼじん)も祀られており、子宝・安産のご利益を求める方々に親しまれています。
心の平安を求める方々や子どもを授かりたいと願う方は、「石手のお薬師さんにお参りに行こう」とお越しください。すべての方々を、暖かく迎え入れています。
遍路の元祖・衛門三郎の再来伝説

当寺のもとの名前は「安養寺」。衛門三郎(えもん さぶろう/以下、三郎)の再来伝説より「石手寺」になりました。
むかし、愛媛県に衛門三郎という豪族(河野家の一族)がいました。家は富んでいましたが、強欲で非道な行為で神仏を敬わず、慈悲の心を持たず、日夜、私利私欲を追求していました。ある日、彼の屋敷を訪ねてきた托鉢(布施を求める行為)の僧を追い払おうと竹ぼうきで鉄の鉢を8つに割ってしまいました。その僧こそ弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい/以下、大師)だったのです。
翌日から、三郎の8人の子が次々に死んでしまいました。 大師への懺悔の気持ちから、田畑を売り払い、家人たちに分け与え、妻とも別れ、大師を追って謝るための旅に出ました。いわゆる四国遍路の始まりです。しかし、20回目もお遍路を重ねても大師に会えず、ついに21回目から逆回りを始めました。
その21回目の途中、徳島の12番札所・焼山寺のふもとで力尽きて倒れてしまいました。その時、大師が現れ「望みはあるか」と尋ねました。三郎は「来世も河野家に生まれ、人の役に立ちたい」と言い残し息たえました。大師は石に「衛門三郎」と刻み、彼の手に渡しました。
翌年、この地方の豪族・河野家に生まれた男の子は、右手を固く握りしめたまま開きません。寺で願いをかけたところ、衛門三郎と書かれた石が現れました。この石を寺に納め、寺の名前を石手寺と改めました。
弘法大師空海とは
弘法大師空海は、讃岐の国(香川県)に生まれた平安時代(774(宝亀5)年~835(承和2)年)の僧で、真言宗の開祖です。幼名は、真魚(まお)といい、貴人の死後に賜る諡號(しごう)を弘法大師といいます。
四国遍路とは
四国遍路とは、約1200年前に弘法大師が修行した88の霊場をたどる巡礼のこと。お遍路をする人のことを「お遍路さん」と呼びます。目的は、健康祈願や近親者の供養、健康増進、自分探しの旅など、人によってさまざまです。日本遺産として認定されています。
寺宝など15の見どころ

1.仁王門【国宝】
仁王門は、河野通継(こうの みちつぐ/鎌倉時代の武士)が、1318(天保2)年に建てたものです。日本全国のなかでも均整がよくとれた門として評価されています。(構造:三間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺)

2.金剛力士像【重要文化財】
金剛力士像は、寺の仁王門に安置されています。左側に安置してある吽形(うんぎょう)の高さは約2.51メートル、右側の阿形(あぎょう)の高さは2.53メートル。お寺の境内を守る役割を担っており、身体は厚みがあります。運慶派の仏師が1240年(仁治元年)に造りました。

3.三重塔【重要文化財】
三重塔は、728(神亀5)年に建てられ、1073(延久5)年に再建されました。高さは約24メートル。鎌倉時代の三重塔のなかで最も優れています。一番下の層の正面には釈迦三尊像を安置し、その後ろには曼荼羅(仏さまの世界を表したもの)が描かれています。(構造:三間三層、本瓦葺)

4.本堂【重要文化財】
本堂は891(寛平3)年に建てられ、1114(永久2)年に再建されました。本堂のなかには、本尊である薬師如来を安置しています。日本の寺院の建築様式と、中国の建築様式の特徴が混じり合った、豪快かつすっきりとしているのが特色です。(構造:桁行五間、梁間五間、一重、入母屋造、本瓦葺)

5.詞梨帝母天堂(子授け石)
【重要文化財】
詞梨帝母天堂(かりていもてんどう)は、高さ約3メートルのお社です。こちらの石を持ち帰ると子授けや安産祈願にご利益があるとされています。無事に子供が産まれたら、その子の名前と生年月日を書き、新しい石を添えて返すのが習わしとなっています。(構造:一間社流見世棚造、檜皮葺)

6.護摩堂【重要文化財】
護摩堂は、室町時代前期(1333~1392年)に建てられました。このお堂で護摩祈祷を行います。境内には伝統的な寺院風・日本風・中国風が混じり合った建築様式の建物が多いのですが、護摩堂は純粋な日本の建築様式なのが特徴です。(構造:桁行三間、梁間三間、一重、宝形造、銅板葺)

7.鐘楼【重要文化財】
鐘楼(しょうろう)は、鐘を吊り下げておくための建物です。室町時代前期の1333(元弘3)年に再建されました。全国的にも珍しい、袴腰(はかまごし:鐘楼の裾が広がっている部分のこと)が付いているのが特徴です。(構造:桁行三間、梁間二間、袴腰付、入母屋造、檜皮葺)

8.銅鐘【重要文化財】
鐘楼(どうしょう)に吊られている、高さ約1.1メートル、径45.5センチの銅鐘です。1251(建長3)年に造られたものと考えられます。経緯は明らかになっていませんが、愛媛県西条市の興隆寺(こうりゅうじ)、愛媛県上浮穴郡久万高原町の大寶寺(だいほうじ)を経て、当寺にやってきました。

9.五輪塔【重要文化財】
五輪塔は、源頼義の供養のために祀られ、2.7メートルの花こう岩製。損害を免れた巨大な塔は、均等な五輪が重厚さと優美さを演出しています。鎌倉時代後期の代表的な石造美術品です。

10.大師堂(落書き堂)
大師堂は、四国八十八箇所霊場の原点である弘法大師を祀る建物です。かつて夏目漱石や正岡子規の落書きがあったことから、「落書き堂」とも呼ばれています。1884(明治17)年に、建てられました。本堂にて本尊・薬師如来さまにご挨拶したあとは、大師堂の弘法大師さまのもとへお参りください。

11.マントラ洞窟
マントラ洞窟は、長さ約160メートルの洞窟です。入口付近の空間は「何が大事かを考える、心の中の悟りの修行道場」、奥の空間は「あらゆる仏菩薩が集まる仏の世界、安らぎと感謝の場」になっています。俗世から離れたひんやり冷たい異空間で、自身と向き合えます。

12.西安大師(日中友好弘法大師像)
西安大師は、高さ16メートル・顔の長さ2.4メートル・筆の長さ3メートルの、弘法大師さまの像です。身体は弘法大師さまが修行した中華人民共和国の西安市の方角、顔は仏教発祥の地であるインドの方角を向いています。松山城や、50番札所の繁多寺(はんたじ)からも姿を見ることができます。

13.衛門三郎の石
四国八十八箇所巡礼の元祖、衛門三郎にまつわる石です。宝物館で展示しています。

14.お茶堂の弘法大師像
弘法大師が自身で制作し、嵯峨天皇に奉納された大師像です。824年(天長元年)に制作。技術や芸術性は高く評価されています。お茶堂に安置され、多くの参拝者に愛されています。50年に一度ご開帳されています。

15.やきもち
五十一番食堂は、参道にある素朴で温かな飲食店です。その中でも、とくに評判となっているのが、石手寺名物の「やきもち」です。伝統的な製法により、素材の旨みを引き立てるよう焼き上げられています。表面はカリッと焼かれ、内部はもちもちとした食感が楽しめます。ぜひ立ち寄ってみてください。
拝観(営業)時間/料金

お茶堂の建物内に納経所があります。御朱印やお守りなどの授与も行っています。年中無休で境内の案内やご祈祷・ご供養の相談などを受け付けております。
納経所:8時〜17時
マントラ洞窟・第二洞窟:8時半~16時半/100円
宝物館:8時~17時/200円(子ども100円)
自家用車駐車場:年中無休/無料
バス駐車場:年中無休/近隣の有料駐車場1,000円